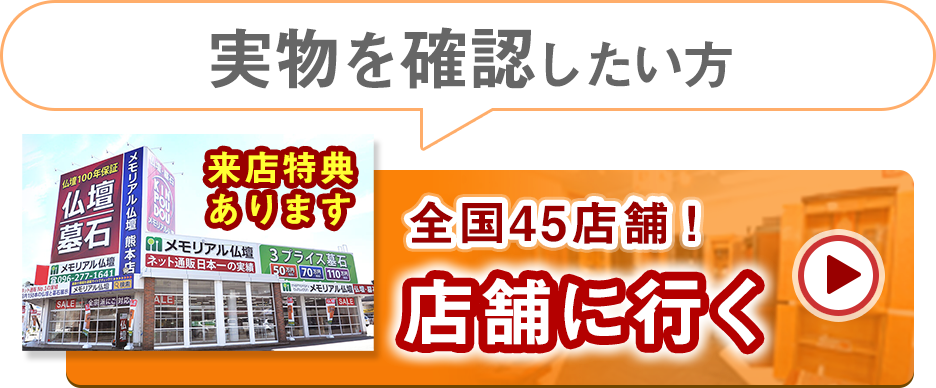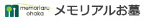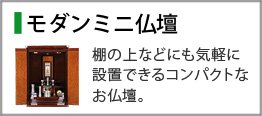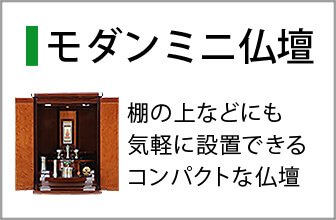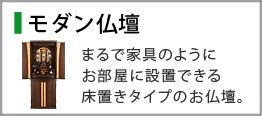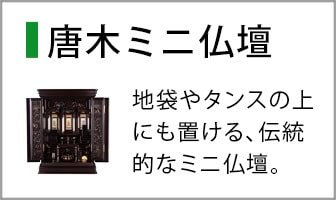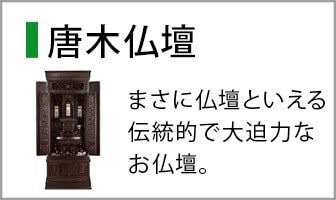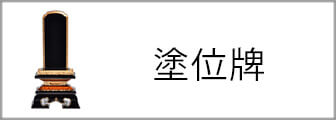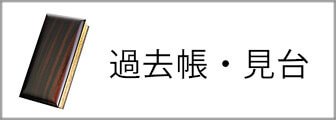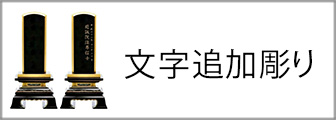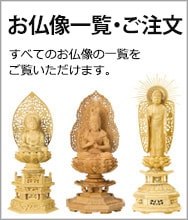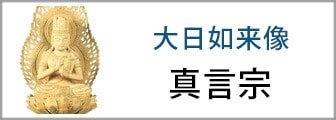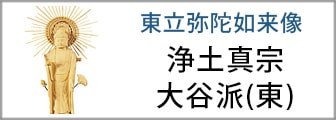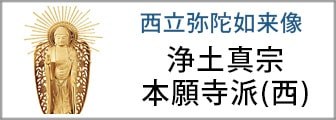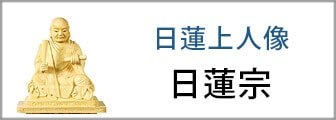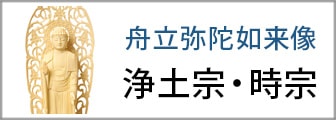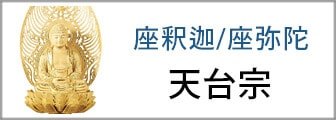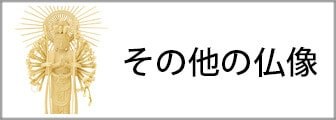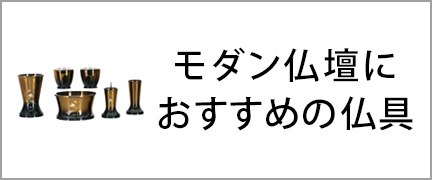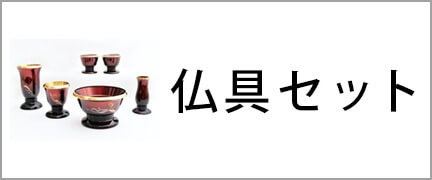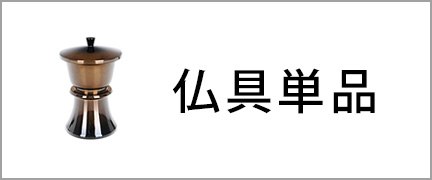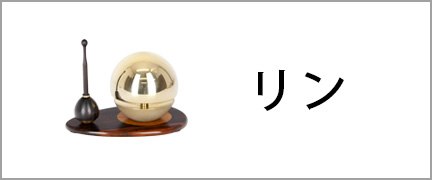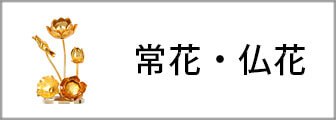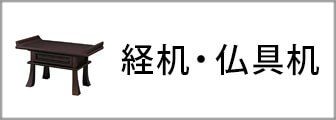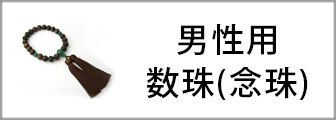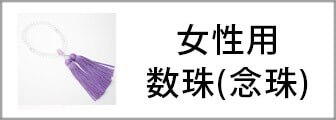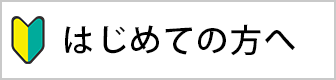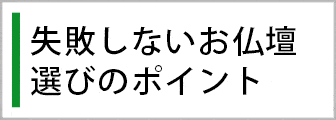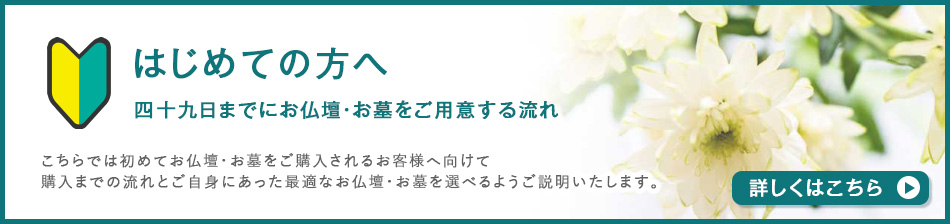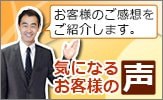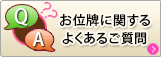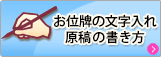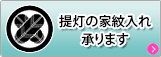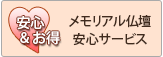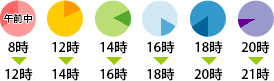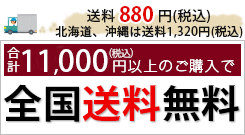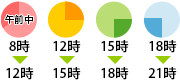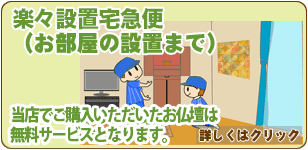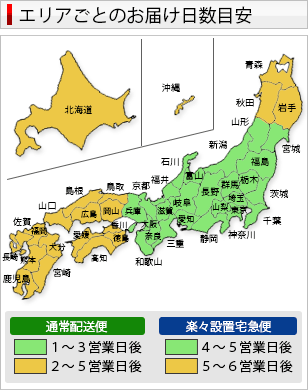位牌の選び方 【更新日】
お位牌をひとつにまとめる方法は先祖位牌や回出位牌そして夫婦位牌があります

お仏壇にはご先祖や亡くなった家族のお位牌が祀られます。
私たちには、いったい何人のご先祖がいるのでしょう?
お位牌というのは世代が移りゆく度に増えてゆくものです。
祖父母の代から両親へ、そして私たちの世代から子どもたちへ、そして孫たちへ…。
そうやってお位牌の数は増え続けてゆくのです。
しかし、お仏壇のサイズは変わりません。
どんなに大きなお仏壇でも、いつかは全てのお位牌が納まり切らなくなる時がやってくるのです。
とはいえ、誰かのお位牌を退かすということもできません。
このようにお位牌が多くなりすぎた時、複数のお位牌をまとめる方法があると言います。
この記事では、ご先祖や故人のお位牌をまとめられるお位牌の種類や作り方、お位牌をまとめる時に必要な供養などについてご紹介いたします。
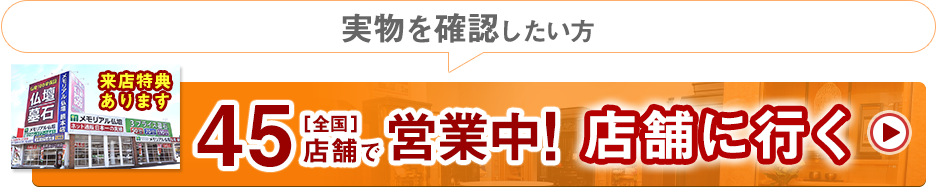
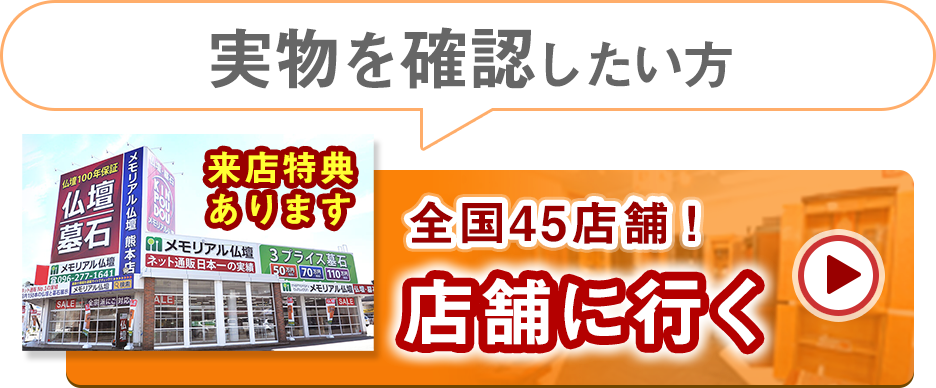
回出位牌ランキング
目次
お位牌をひとつにまとめる必要があるのはまずお仏壇にスペースがなくなった時です

お位牌とはご先祖や故人の戒名を記した木牌のことですが、ここには亡くなった方の霊魂が宿るとされ、故人そのもののように大切に扱われます。
故人の象徴であるお位牌は、ひとりの故人に対して1柱(位牌の数え方)用意されるべきものです。
ご家族の誰かが亡くなった時のご葬儀では白木の位牌が用いられ、その後四十九日法要まではご遺骨やご位牌と共に祭壇に祀られます。
仏教では亡くなった方の魂は行き先が定まらず彷徨っていて、四十九日を過ぎて初めて成仏(じょうぶつ)できると考えられ、それまでは仮の位牌である白木位牌が安置されます。
残されたご遺族は四十九日法要の日までに、故人のための本位牌を用意しなければなりません。
そして四十九日法要の時に、白木の仮位牌から本位牌に故人の魂は移され、その後はお仏壇に安置されてご家族に供養されることになります。
しかし、この時すでにお仏壇がご先祖や亡くなった家族のお位牌で埋まっていて、新しいお位牌を置くスペースがないことがあります。
このような場合は、それらのお位牌をまとめる方法を考えなければなりません。
複数のお位牌をひとつにまとめる時には、3つの種類のお位牌が使われます。
お位牌をまとめるときに先祖位牌を使う場合は過去帳に故人の情報を残しましょう
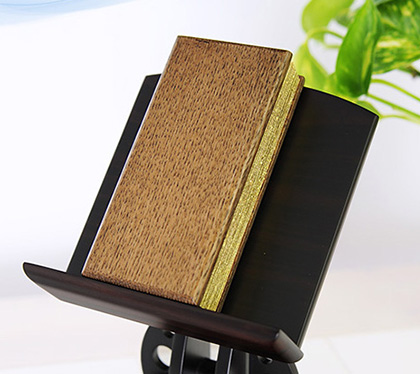
お位牌をひとつにまとめる方法としては、まず「先祖位牌」があげられます。
これは複数のご先祖のお位牌を、1柱の先祖位牌にまとめるという方法です。
お位牌の表面には「〇〇家先祖代々之霊位」と記しますが、宗派によってはその上に梵字や冠文字、家紋等を入れたりします。先祖位牌の裏面には何も文字入れしません。
通常お位牌の表面には故人の戒名(かいみょう)と没年月日、裏面には俗名と享年が記載されるのですが、先祖位牌の場合はそのような個人個人の情報を入れられません。
先祖位牌を作った後は、もう使わないご先祖のお位牌は菩提寺などでお焚き上げ処分されます。
そうすると、ご先祖の名前や死亡年月日などの記録が残らなくなりますので、「過去帳(かこちょう)」にご先祖の戒名と俗名・没年月日と享年を書き写し、「見台」にのせてお仏壇に飾っておくといいでしょう。

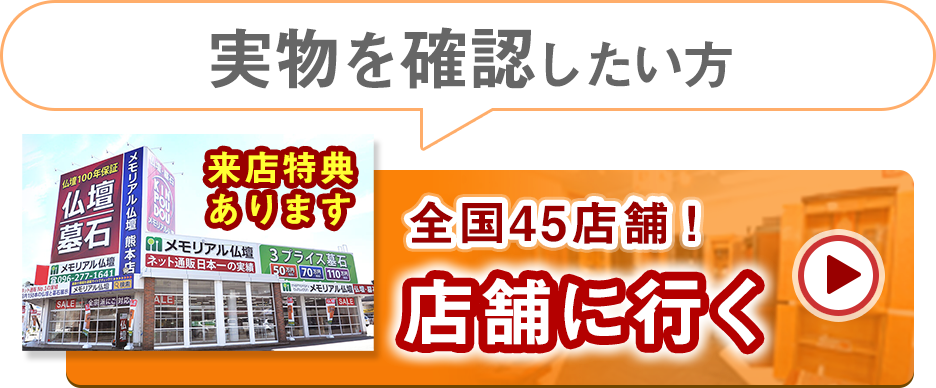
複数のお位牌をまとめるには回出位牌が便利です

「回出位牌 (くりだしいはい)」とは箱型をした少し大きめのお位牌で、中に数枚の札板が入っているものです。
繰出位牌(くりだしいはい)と書かれる場合もあります。
この回出位牌を使うと、一枚一枚の札板に「ご先祖や故人の戒名・没年月日・俗名・享年」をそのまま書き写すことができるので、過去帳などを使う必要はありません。
ひとつの位牌に10枚前後の札板の収納が可能なので、たとえば20人分の故人のお位牌ですと2柱の回出位牌にまとめることができます。
この方法だとお仏壇のスペースが限られていても、多くのご先祖や故人の情報を残した状態でお位牌を祀ることができるので大変便利です。
札板は一番上に「〇〇家先祖代々之霊位」と書いた札を置き、1つにまとめた位牌であることが分かるようにします。
そして二番目の札からは、命日が近い順番に札板がくるよう入れておきます。
そして命日が過ぎたら一番後ろに回します。
こうして札板を回して、命日が近い順にご先祖の札板を出していくことから「回出位牌」と呼ばれています。
最初から回出位牌をお位牌として選ぶということはまず無いですが、ご先祖から受け継がれたお位牌の数が時と共に増えて、お仏壇が少し狭くなってきた場合などに買い替えられます。

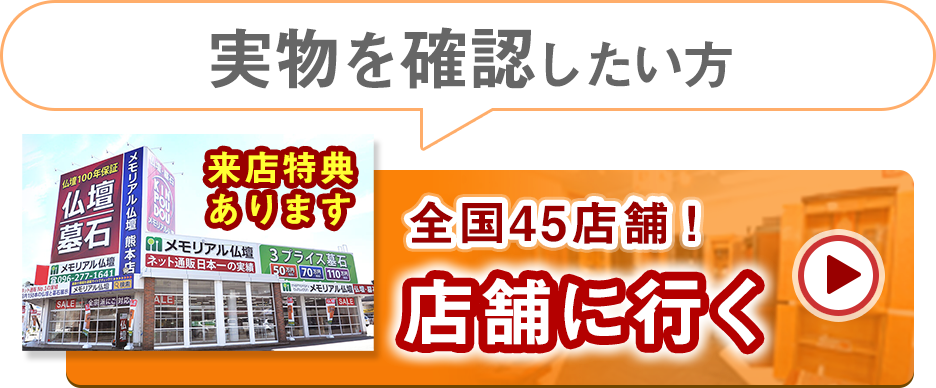
お位牌をまとめる方法には夫婦位牌というのもあります

「夫婦位牌(めおといはい)」は、2柱のご夫婦のお位牌を連名にして1柱にしたものです。
夫婦位牌を作る理由は先祖位牌や回出位牌と違い、お仏壇のスペース問題とは関係ありません。
故人の遺言から作ったり、仲の良かったご両親が亡くなった後や、別々のタイミングで作った2柱のお位牌の差がないようにと、子どもたちが夫婦位牌を作る場合が多いです。
夫婦位牌の文字入れは、表面にお二人の戒名を連名で入れ、裏面には没年月日、年齢、俗名などを入れます。
夫と妻のお位牌への名入は、宗派やお寺さんで異なる場合がありますので事前の確認が必要です。
夫婦位牌には、ご夫婦の戒名や命日などを並べて文字入れできるよう、札幅が横に長い「巾広位牌」が使われます。
他のお位牌よりも文字入れする文字数や行数が多くなるため、4寸以上のサイズのお位牌の購入をお勧めします。
お位牌をまとめる際にはきちんとお位牌の供養をしましょう!

お位牌をまとめる際には、古いお位牌と新しいお位牌の供養をする必要があります。
この供養は、ご僧侶に自宅まで来ていただくか、菩提寺に今まで使っていた複数のお位牌と新しい1柱のお位牌を持っていって執り行われる儀式です。
お位牌の閉眼供養
まずお位牌をまとめる場合には、これまで使っていたお位牌から故人の魂を抜いてもらう「閉眼供養(へいがんくよう)」という儀式をする必要があります。
この儀式は宗派や地域によって、お性根抜き(おしょうこんぬき)や「魂抜き」など色々な名前で呼ばれます。
魂抜きにはお位牌に宿ったご先祖の魂を天に返してあげるという意味があり、供養の後のお位牌は単なる木の板となります。
関連記事
・「お位牌は魂抜きをしてお焚き上げするか永代供養に出して処分します」
古いお位牌の処分
閉眼供養をした後の古いお位牌は、そのままお寺で処分していただくことも可能です。
その場合は「お焚き上げ」という焼却処分がされますが、最近は環境問題に配慮して、火を焚かないというお寺さまもあるそうです。
魂が抜かれたお位牌は単なる木札と変わりないため、一般のごみとして処分することもできるのですが、やはりバチあたりになると気が引ける人が多いと思います。
その場合は、やはり菩提寺でお焚き上げ処分をしていただいた方がいいでしょう。
木札の処分が正式にされているか気になる場合は証明書を出してもらうこともできます。
お位牌の開眼供養
新しく作ったお位牌は「開眼供養(かいげんくよう)」と呼ばれる供養をすることで、初めて真のお位牌としての役割を持つようになります。
閉眼供養の時の反対で、ご僧侶にお位牌に故人の魂を入れていただきます。
ここでご紹介したように、お位牌をひとつにまとめる方法は複数あるので、その中から自分の宗派やお仏壇のスペース、好みのご供養の形に合わせてお選びいただけばいいと思います。
どの種類のお位牌でまとめるにしろ、複数のお位牌をひとつにする際には開眼供養・閉眼供養・お焚き上げの供養が必要ですので、あらかじめ菩提寺や仏壇店に相談しておくといいでしょう。